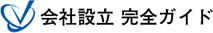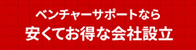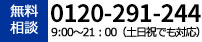- TOP|会社設立
- ›
- 起業の基礎知識と手順|現状分析・資金調達・開業手続きまで徹底解説【起業の世界Vol.1】
- ›
- 知っておきたい起業のリスク【起業の世界vol.4】
知っておきたい起業のリスク【起業の世界vol.4】

この記事の執筆者 税理士 森健太郎
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

知らなければ損をしてしまうたくさんの法律やルールが、株式会社や合同会社を起業する際には存在します。こうした落とし穴にハマらないためにも、事前にしっかりとしたリスクヘッジをしておきましょう。
リスク①
消費税の免税を受けるために資本金に注意
株式会社にせよ合同会社にせよ、法人を設立してから2期の間は消費税の免税が認められています。
ただし、これは資本金が1000万円未満の企業に限られたルールです。
資本金が1000万円以上の場合には、第1期の決算から消費税が課せられてしまうのです。
「資本金といえば、1000万円のイメージだから、そうしておこう」という安易な決め方をすると、あとで泣くことになります。
仮に事業がうまくいって、第1期の決算時に3000万円の課税売上があった場合には、たとえ収支が赤字で法人税等が課されなかったとしても、課税仕入れが半分だったとして第1期に120万円、第2期にはそれ以上の余計な税金を払わなければならないのです。
また、資本金が1000万円未満であっても、スタートアップの期首から6カ月の期間で売上が1000万円、給与も1000万円を超える場合には、1年目から消費税の支払いが求められます。
これだけの給与を初期から計上する企業はそれほどありませんが、個人事業から法人成りした場合には、それなりに見られるケースです。
その場合、第1期の事業年度を7カ月以下、2期目の事業年度を12カ月にすれば、最長で19ヵ月の消費税免税が可能です。
リスク②
第1期の事業年度に要注意
これはリスク①とも大きく関わってきますが、事業年度の期間によって課税のリスクが増大することがあります。
基本的に多くの企業が暦通りに4月~翌年3月末の1年間を事業年度としていますが、決算時期を自由に決められるのが法人の強み。そのため、6月スタートの翌年5月末決算でも、10月スタートの翌年9月末決算でかまわないのです。しかし、一般的な例に従って特に深く考えないまま、3月末を決算期にした場合は、のちのち面倒なことになってしまいます。
では、一例をあげてみましょう。たとえば前職の退社時期など、もろもろの事情から第1期を3月にスタートさせた場合、その3月末のわずか1カ月の時点で決算を迎えることになります。リスク①でも説明したように、消費税が免税されるのは起業から2期の間だけですから、このケースで言えば翌年度の12カ月を加えた13カ月以降は消費税の支払いが求められるということになります。
これは本当にもったいないので、決算期は熟考してから決めるようにしましょう。
リスク③
設立後の税務署への届け出必須
法人には、「繰越欠損金の損金算入」という個人事業主にはない特別ルールがあります。
法人税法では、その年に発生した赤字に対して、翌事業年度から10年間以内の黒字と相殺できることが認められているのです。
たとえば、創業年度に売上があがらず、諸経費だけで1000万円の赤字を出してしまったとしても、翌年度に2000万円の売上がある場合には、相殺して1000万円の黒字で計上できます。
しかし、この法律の適用を受けるためには、会社を設立してから3カ月以内に青色申告の承認を受けなければなりません。また、青色申告の届出がなければ、10万円以上30万円未満の消耗品を1年で全額経費にすることもできません。
たとえ、書類の作成を司法書士に任せていたとしても、税務署への届出書の提出は設立後であるために司法書士にその責任はなく、自身で行わなければなりません。心配であれば、税理士や弁護士なども含めてワンストップで書類の作成や届け出を行う事務所への相談をお薦めします。
リスク④
役員報酬は1年間変更できない
ここまで何度か言及してきた通り、役員報酬は「定時定額支給」が原則のため、その年度の間は基本的に固定でなければいけません。
もし変動させてしまった場合は、その年度内でもっと低い役員報酬が1年間続いたものと見なされます。さらに、その差額は役員賞与とされてしまうため、すべてを経費としては認められず、余計な税負担が発生してしまうことになります。
たとえば、営業系企業が社長を含めた役員の給与を出来高制にした場合の話をしましょう。仮に、もっとも給与額の少ない月が10万円、多いときで300万円あり、合計で年額2000万円の役員報酬を受け取ったとします。このケースでは毎月の役員報酬は最低額の10万円と見なされ、年額で120万円。残りの1880万円は役員賞与の扱いとなり、法人税法上では損金にならないため、余計な法人税がかかってくるのです。
創業初期には非常に多い失敗事例ですので十分に注意してください。
リスク⑤
給料を払ったら翌月10日には源泉所得税を払う
リスク④の役員報酬に続き、給与に関しての落とし穴です。ここでは、源泉所得税について言及しましょう。
源泉所得税とは、収入から所得控除を差し引いた金額に一定の税率で課されるものです。本来、所得税は従業員が税務署に支払わなければいけませんが、会社が源泉徴収という形で給与から差し引いて支払っています。外部業者などに対する報酬も同様の処理を行います。
この源泉所得税ですが、通知や納付書が税務署から毎月送られてくるものではありません。役員報酬や従業員への給料を支払った場合、その所得税は翌月10日までに納めなければなりません。創業したばかりの経営者の場合、この納付を失念するケースがあとを絶ちません。
仮に、15名の従業員に対してそれぞれ40万円の給与を支払ったとします。そして、社長自身も100万円の役員報酬を受け取っていた場合は、その合計額700万円に対して、約38万円の源泉所得税を支払う義務があるのです。さらには前述した通り、支払い日の翌月10日までに納めなければならず、この納付が遅れた場合には、3万8千円の罰金を科せられてしまいます。創業したばかりの経営が安定していない企業にとって、これは大変な痛手です。
「給料を支払ったら、翌月の10日までに源泉所得税を納める」ということを頭に入れておきましょう。
リスク⑥
経費には落ちるものと落ちないものがある
経費も経営者にとっては難しい問題です。何が経費として計上できて、何が経費にはならないのか。この点をよく理解していなければ、またも余計な支払いに頭を悩ませることになります。
ここでは創業初期に経費と“勘違い”しがちなものをリストアップして説明していきましょう。
業務の際に身につけるスーツ、時計、かばん、くつ、それに伴うクリーニング代などは法人で経費として計上できません。
また、家族だけで経営している企業においては健康診断や忘年会、親戚への結婚祝い、英会話スクールやスポーツジムの入会金と月謝、個人の生命保険料が経費として認められないので注意が必要です。
さらには社員旅行に関しても、家族経営の企業の場合、“ただの家族旅行”と見なされ、経費にはなりません(ただし、血縁関係のない従業員での社員旅行は別の扱いになります)。
また、会社の通帳やクレジットカードから支払った経費は、内容次第で賞与と判断される場合があり、その際は法人税に加えて、源泉所得税も発生する可能性があります。十分に注意してください。
リスク⑦
会社設立前に払った費用も経費になる
リスク⑥に続き、こちらも経費に関する落とし穴です。会社を経営し始めてからかかる費用は当然、経費として計上できるため、法人名義で領収書を発行してもらうのが常識です。
しかし、多くの方が見落としがちなのが、会社を設立する前に発生した経費。たとえば、業務に必要なパソコンや事務機器、テーブルや椅子などを購入した費用は、たとえ起業前であっても経費として計上できるのです。それを知らないがために、結果的に持ち出しとなって損をするケースが実はかなりあります。
こうした費用は創立のための経費、つまり、創立費として法人の経費とすることができます。また、これらに加えて、登記印紙代、交通費、ハンコ代、打ち合わせに使用した飲食費なども創立費の一部となります。何でも経費にはできませんが、“可能性を考慮”して領収書を取っておきましょう。
リスク⑧
税制改正が頻繁に行われる生命保険に注意
法人契約の生命保険は会社の経費として計上できます。そのため、たとえ月々の支払いが高額だったとしても、健康面などのリスクを考え、加入する経営者は少なくありません。
そして、それ自体は何の問題もないのですが、生命保険に関してはひとつ厄介な点があります。それは、生命保険に関する税制が頻繁に改正されることです。そのため、税制改正以前は特段問題にならなかった保険が、ある日以降の契約は経費にできないというケースもあります。特に生命保険は払い戻し金に大きな利息がつくなど、一見お得に見える商品がラインアップされているため注意が必要です。
また、冒頭にも記したように、多くの社長は経営や健康のリスクヘッジを考慮して、高額な生命保険に入りがちです。もし、加入を考えているのであれば、事前に税理士などに相談をしてから、加入することをお薦めします。
リスク⑨
融資を想定した設立・会計処理をしよう
事業の拡大など、銀行から融資を受けられるのが法人形態をとることの大きな強みです。
しかし、ひとつ間違えれば、融資を非常に受けづらい状況になってしまいます。そのポイントとなるのが、資本金です。
たとえば、赤字が重なって経営が苦しくなり、銀行に融資を依頼したとします。その際、多くの銀行が重視するのは貸借対照表の「純資産の部」と呼ばれるものです。これは、「資本金+繰越利益(-繰越損失)+当期利益(-当期損失)」という計算式で算出されます。この値がマイナスになると債務超過と見なされ、まず融資を受けられません。
特に資本金がポイントで、資本金の額が大きければ大きいほど債務超過にならないで済むのです。会社法の改正により、1円の資本金でも会社を設立できるようになりましたが、こうしたリスクを考えて、安易な資本金の設定をしないようにしましょう。
リスク⑩
助成金・補助金は申し込むタイミングが大事
創業間もない段階は資金不足に悩まされがち。こうした状況を打破してくれるのが、国や都道府県など行政が行っている補助金・助成金です。“タダでお金をもらえる仕組み”のため、ぜひとも利用したいころですが、タイミングを逃せば利用できなくなるので、その点は注意が必要です。
また、実際には後払いとなるため、支給のタイミングを読み違えると、あてにしていた支払いに間に合わないというケースも出てきます。
さらには、「補助」「助成」という名前がついている通り、あくまで事業をサポートすることを目的としたお金です。そのため、補助金や助成金には補助率という考え方があり、たとえば補助率が3分の2の場合、事業者が300万円を支出したのであれば、200万円が支給されます。
あくまで、自分で支出した金額を後から補填してもらうという仕組みですから、極端にあてにするのは危険です。
利用できる主な助成金・補助金
①創業補助金・事業承継補助金
前者は新たに事業を始めた人向けの補助金で50~200万円、後者は事業を引き継ぐ予定の人を対象にしたもので100~500万円が支給されます。
②小規模事業者持続化補助金一定の基準を満たした小売業
一定の基準を満たした小売業やサービス業などの小規模事業者を対象とした補助金。最大50万円、複数で共同の場合は100~500万円が支給されます。
③キャリアアップ助成金
従業員への福利厚生を充実させた事業者に対して国が支給する補助金。パートから正社員への登用など、合計8つのコースが用意されています。
④地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型)
都道府県と中小機構が作ったファンドが中小企業者に支給する助成金。特に、地域コミュニティへ高く貢献する取り組みに支給される傾向があります。
▼ 起業の世界
- 起業の世界Vol.1 起業の基礎知識と手順|現状分析・資金調達・開業手続きまで徹底解説
- 起業の世界Vol.2 起業前にするべき自問自答
- 起業の世界Vol.3 これからの働き方 ~“起業”という選択肢~
- 起業の世界Vol.4 知っておきたい起業のリスク
- 起業の世界Vol.5 起業した人の属性とキャリア
- 起業の世界Vol.6 資金調達について
- 起業の世界Vol.7 起業後の状況
- 起業の世界Vol.8 起業する前におさえよう!法人の種類による違いと特徴とは
- 起業の世界Vol.9 会社設立のメリット・デメリットを知ろう
- 起業の世界Vol.10 出資、融資、補助金・助成金の違い
- 起業の世界Vol.11 資金の調達①出資とファンド
- 起業の世界Vol.12 会社設立する前にチェックしておくべき起業家の5つの心得
- 起業の世界Vol.13 独立・起業・自営業に向いている?独立後に失敗をしてしまうタイプ7選
- 起業の世界Vol.14 会社の年間手続きスケジュールを知ろう
- 起業の世界Vol.15 社会保険と給与計算
- 起業の世界Vol.16 会社員と起業家ってどう違うの?
- 起業の世界Vol.17 起業したら税金は自分で納めるのが原則?
- 起業の世界Vol.18 起業費用はいくら?法人と個人事業主の相場を解説!
- 起業の世界Vol.19 固定費について詳しく説明
- 起業の世界Vol.20 起業時の資金調達と自己資金の目安から助成金・節税まで
- 起業の世界Vol.21 今更聞けない 借入金と出資金の違いについて
- 起業の世界Vol.22 無担保 無保証の制度について説明
- 起業の世界Vol.23 誰にお願いする?連帯保証人のお願いの仕方から選び方について
- 起業の世界Vol.24 一人で起業するメリットから 雇用のタイミングまで
- 起業の世界Vol.25 外注費用は節約しましょう
- 起業の世界Vol.26 起業を目指す人必見!起業家7人に成功例や失敗例など経験を聞いてみた!
- 起業の世界Vol.27 税理士が教える 起業・開業後の1年目のスケジュール
≫ 会社設立は超かんたん!?何も知らないド素人があっさり起業した話【会社設立手続き】 ≫ 合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!